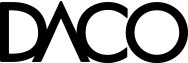8月に1冊の本が出る。『アジアがいる場所』(光文社)。日本のなかのアジアの話だ。台湾の過激な独立派、史明が営んでいた池袋の中華料理店、忽然と消えた荒川沖のリトルバンコク、日本で生きるミャンマーの少数民族……。
そのなかで沖縄のにおいについて触れている。はじめて沖縄の土を踏んだのはもう、35年以上前だ。そのとき、バンコクから台北に向かい、そこから船で石垣島に渡り、さらにフェリーで沖縄本島に着いた。そのとき、那覇では牧志の公設市場にも行っているはずなのに、ほとんど記憶がない。
それから何年かが経ち、再び沖縄に向かった。東京から飛行機で那覇に向かった。なぜ再び、牧志の公設市場に向かったのかは覚えていないが、そこに流れるにおいに、水に落ちたドライアイスのように反応してしまった。寒気すら覚えた。少し怖いほどだった。そこにはアジアのにおいがあったのだ。
はじめて沖縄の土を踏んだとき、僕の臭覚が反応しなかったのは、おそらくアジアの感覚のまま、沖縄に辿り着いたからだろう。
公設市場で激しい臭覚反応を起こした僕は、簡単に沖縄病に感染する。かなりの重症で、月に1回以上沖縄に通うという沖縄フリークの道を一気に進むことになる。
僕が沖縄に求めたものはアジアだった。「ちきあぎ」に出合ったときは箸が震えた。タイのトートマンプラーそっくりだった。この「ちきあぎ」が本土に渡り、さつま揚げになる。東南アジアから渡った蒸留酒の手法が泡盛を生み、本土に渡って薩摩焼酎に変身する。サツマイモは沖縄では、単に「いも」という。
東南アジアの食材のマッシュアップを担ったのは琉球王朝の商人たちだった。琉球王朝は中国との朝貢貿易を行っていた。これは中国の王朝に貢物を届け、その見返りに中国の物産を受けとり、それを東南アジアで売りさばくという中継貿易だった。日本と中国の間にある小さな島国の処世術だった。
琉球王朝の人々は商才を発揮する。ベトナムのフエに出向き、朝貢貿易がいかに儲かるかを伝えたかと思うと、タイのアユタヤでは、「朝貢貿易をしてもほとんど儲かりませんよ。琉球と直接、貿易をした方がいい」などと口にする。つまりは、自分たちの利益を増やすために、口八丁手八丁……。
その眼鏡に適った料理が東南アジアから沖縄に渡ったのだろうか。
しかしその後、沖縄は変貌していく。太平洋戦争では地上戦の犠牲になり、アメリカの統治下に入る。そして本土復帰。近々の10年は急激に本土化が進んでいる。日本とアジアの真んなかにいて、違う文化を融合させていったダイナミズムは薄れてしまった。「ちきあぎ」を知らない沖縄の若者もすでに多いという。