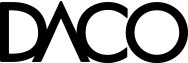Contents
針と糸に見つけた
もうひとつの“自立の種”
「支援するってことは、一方的に“作ってあげる”ことじゃないんです。何が最善かを一緒に考えて、自立するために必要なものを一緒に作る。そうじゃないと、続かんのですよ」
タイ北部の山岳地帯に暮らすモン族の村に通いはじめて、佐伯昭夫さんは31年になる。
村が本当に自立するためには、どうすればいいのかーー。佐伯さんがたどり着いた答えは、「自分たちで食べるものを、自分たちで作る」ことだった。野菜や米、果物を育てて自給自足し、余った作物を売れば、現金収入も得られる。そんな農業の知識を伝えていった。
さらに、子どもたちが不衛生な場所で遊ぶ姿を目にして、安全で環境にやさしい“エコトイレ”の整備にも取り組んだ。衛生環境は劇的に改善され、微生物の力で浄化し、液肥に生まれ変わった排泄物は、畑に実りをもたらすようになった。村にとって理想的な“循環”が、確かに生まれはじめていた。
そして佐伯さんは、「自分たちの手で生み出す支援」の可能性を探る中で、村の女性たちのなかに、もうひとつの“種”を見つけた。それは、“針と糸”だった。
「これ、かわいい!」の声が
村の女性たちの心に火を点けた
モン族の女性たちは、もともと刺繍の名手だ。布にびっしりと施される幾何学模様や、鮮やかな色使い、繊細な縫い目……。手間暇かけた刺繍が施された民族衣装は彼女たちの誇りであり、母から娘へと受け継がれる“文化そのもの”なのだ。
「この技術、なんかに使えんかなって思ったんです」
佐伯さんが最初に提案したのは、財布やペンケース、小さな巾着袋を作ってみることだった。現地で材料を調達し、サンプルを作って見せた。
「こんなん作れそうか?」
と聞くと、女性たちは一斉に「できる!」と答えた。
ただ、実際に仕上がったものは、お世辞にも売り物にできるような代物ではなかった。
「縫い目がガタガタでね、これじゃ売れん。でも、持ち前の技術はある。だったら“磨けば光る”はずなんです」
佐伯さんは、縫製の基礎をイチから教えた。糸の締め方、布の折り返し、ミシンの使い方。地道な練習を繰り返すうちに、少しずつ製品の形になっていった。
形になったものを日本からの訪問者や支援者に少しずつ渡していくうちに……、
「これ、かわいい!」
「どこで作ってるの?」
そんな声が返ってきた。
「そういった声を聞いたとき、村の女性たちの顔がね、パァッと明るくなったんです。“私たちの作ったものが、誰かの心に響いた!”っていう実感を感じたみたいでね」
現地の人たちにとって「何かを生み出すことで、それが価値を持つ」という体験は、人生で初めてのことだったのかもしれない。消費者からの反応ひとつで、村の女性たちのやる気が俄然向上した。
タイ語が話せると、世界が広がる
刺繍グループが軌道に乗り始めた頃、佐伯さんはもうひとつの“芽”にも気がついた。
支援のモン族は、ラオス内戦でタイの山岳地に追われた難民の人たちで、公的教育やタ社会など政府の制度とは長らく距離があった。それ故、村に保育園を作り、給食が始まり、教育を受けた子どもたちが“タイ語を話せるようになった”というのは、実はとてつもなく大きな変化だったのだ。
そして、その姿を見た母親たちが動いた。
「うちの子が勉強しとるんだから、私もやりたい!」
女性たちは自主的に“タイ語勉強会”を始めた。読み書きを練習し、役所に行く用事ができたときは自分自身で話す。
「そしたらね、役場の職員が驚いたって言うんですよ。“モン族で、自分で字が書ける人なんて見たことない”って」
その勉強会をきっかけに、村の中で“教える人”と“学ぶ人”が生まれた。やがて他の村からも「教えに来てくれ」と声がかかるようになった。
どんどん拡がる「小さな成功体験」と
ポジティブな空気感
こうして、エコトイレも刺繍グループも、タイ語勉強会も、すべて“自分たちでやってみたら、できた”という成功体験が原動力になって、村の中にポジティブな波動が広がっていった。
佐伯さんは言う。
「どこもかしこも全部やろうと思っても無理。だから最初はひとつの村だけ、ちゃんとモデルを作る。そうすればそれが自然と周りに波及していくものなんです」
今、佐伯さんが関わってきた村々では、それぞれの形で自立が進んでいる。農業で収入を得る家族もいれば、織物や果物の加工品を作って販売する女性グループもいる。村のリーダーが集まって、地域会議を開くようにもなった。
「もう、私がいなくても大丈夫なぐらい、みんなちゃんとやってるんです」
“いなくても大丈夫”を
これからも見届けていく
村の人々に自立の精神が根付いた今でも、佐伯さんは定期的に村を訪れる。若い頃のように頻繁には通えなくなったけれど、エコトイレの技術支援や、視察のサポート、助成金の報告業務など、まだまだやることは多い。
「でも、基本はもう、村人たちに任せとるんです。昔みたいに“してあげる”ことはしません。ちょっとした材料代くらいは支援するけど、それも今はほとんど現地で村人たちの手でまかなえるようになった」「多くのリーダーも育った」
そう話す佐伯さんに、最後にひとつ聞いてみた。「支援してきた中で、一番うれしかった瞬間って、どんな時なのでしょう?」
少し考えたあと、佐伯さんは言った。
「やっぱり……、“トイレが詰まらなくなった”って言われた時かな」
たったそれだけの言葉。でも、この短い言葉の中には約31年分の膨大な想いと歩みが詰まっている。誰かに作ってもらったものではなく、自分たちの手で、考えて、試して、失敗して、やっと完成したもの。その“成果”が、ちゃんと機能している。そして、それを、あたりまえのように受け入れている村の人たちがいる。
「これはね、本当にすごいことなんですよ」「みなさん“笑顔をありがとう”」
そう言って、佐伯さんは少し笑った。もちろん、まだまだこれからも佐伯さんの北タイ村通いは続く。
(取材・文/平原千波)
佐伯昭夫さんが受賞した「社会貢献者表彰」とは
「社会貢献者表彰」では、広く社会のため、人のために尽くされている方を募集しています。
公益財団法人社会貢献支援財団は、1971年(昭和46年)より「社会貢献者表彰」事業を始め、毎年表彰を行っています。この表彰は、国内外において社会と人々の安寧・幸福のために尽力し、顕著な功績を挙げながらも報われる機会の少なかった方々を讃えるものです。 表彰対象者の選定は、一般の方からの推薦に基づいて行われます。皆さまからの推薦を心よりお待ちしております。
<対象となる功績>
● 困難な状況の中で努力し、社会の安寧や幸福のために尽くされた功績
● 先駆性、独自性、模範性などを備えた活動により、社会に尽くされた功績
● 海の安全や環境保全、山や川などの自然環境や絶滅危惧種などの希少動物の保護に尽くされた功績
など推薦方法の詳細は当財団のウェブサイトをご覧になるか事務局までお問い合わせください。
WEB:www.fesco.or.jp
推薦フォーム<候補者について>
●年齢・職業・性別・信条などの制限はありません。
●日本で活躍する方、もしくは海外で活躍する日本人を対象とします。
公益財団法人 社会貢献支援財団
WEB:www.fesco.or.jp
Facebook:www.facebook.com/fescojp
E-mail:fesco@fesco.or.jp