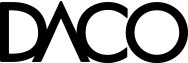旅行に出る理由は人それぞれ。その時々の興味や気分によっても変わってくると思いますが、その中に「あの人に会いたい」という理由があってもいいですよね? 本コラムでは、タイ各地で暮らす日本人をDACO編集部が直撃。インタビューを通してそれまでの歩みや現地での活動を紐解くと同時に、その近隣の魅力的なスポットをご紹介していきます。

アクセス:バンコク→ウドンターニー県(飛行機で約1時間)→ノンブアランプー県市街地へ(車で約1時間)・エリア:東北部・特徴:タイで最も新しい県の一つで、素朴かつダイナミックな自然が魅力。・主な観光地:エラワン洞窟、タム・クローン・ペーン寺院、プー・カオ・プーパン・カム国立公園・DACO編集部が取材した観光・グルメ紹介記事はこちら
1990年、東京都生まれ。東京農業大学オホーツクキャンパスに在学中にスィリポーンさんと出逢い、2020年3月にタイ・ノンブアランプー県に移住。21年4月、手織り・藍染工房「SILK & HOPE」スタート。現地の職人と共に天然藍染めを使った商品を製作・販売している。趣味はドライブとカフェ巡り。
奥さんとの出逢いで人生が変わる
コロナ禍に見つけたモノづくりの道
バンコクから東北へ500km以上離れた場所にあるノンブアランプー県は、タイで最も新しい県の一つ。タイ人でさえ行ったことがない人が多いこのエリアに、「何もない」という印象を抱く人もいるかもしれません。野口さんは2020年3月、奥さんのスィリポーンさんと共に県内にあるグッヘー村に移住。翌年4月に、手織り・藍染工房「SILK&HOPE」をオープンさせました。
「ここで暮らしているのは、妻の生まれ故郷である村の発展に貢献するためです。僕が東京農業大学で食品加工に関する知識・技術を学んでいた頃、留学生として同じ学部に在籍していたのが妻でした。当初は全く関わりがなかったのですが、研究室が一緒になったことをきっかけによく話すようになりました」。スィリポーンさんは当時から故郷に対する想いを口にしていたと、野口さんは振り返ります。
「妻が育ってきた村は、決して恵まれた環境ではなかったそうです。農業主体の村であり、当時の妻の家族の収入は年収8万Bほど。家族を助けるため、学校以外はアルバイトをしたり農業の手伝いをしていたのだと。今も同じような環境で生きる村の子どもたちのためにも『いつかは故郷に帰って、村のために、タイのために生きたい』ということを僕に話してくれました」。
スィリポーンさんの想いに心を動かされ、野口さんがタイで暮らすことを決心したのは社会人2年目の頃。その後は移住資金を貯めるため、スィリポーンさんと共にホテルでの住み込みの仕事に就き、ノンブアランプー県への移住を果たすのでした。
村に根づく伝統技術を生かした新しいモノづくり
移住当初は、飲食店や日本語教師など現地で何ができるのか模索中だっという野口さん。知人に紹介された手織りと藍染めの職人と出会ったことをきっかけに、タイの伝統技術を使った製品づくりに舵を切ります。「ノンブアランプー県の手織りや藍染め製品は、OTOP(タイ政府が薦める1村1品運動)にも選出されている伝統的なもの。出来上がった製品の細やかな仕上がりも魅力的で、もっと多くの人に知ってもらいたいという想いもあり、工房の立ち上げを決めました」。
「SILK&HOPE」で使用する原材料は、すべてタイ産。藍は、ティントリアという品種の天然藍を使用しています。当初は藍の栽培を生業としているサコンナコン県の農家から仕入れていましたが、その品質にムラがあり、野口さんはどうしても納得がいかず。去年からはスィリポーンさんから譲り受けた40ライ(1ライ=1600㎡)の畑を使い、試験的に藍を育てている最中なのだそう。
もちろん野口さんにとって、藍を栽培するのは初めてのこと。大学時代に学んだ畑作りの知識を掘り起こし、周囲に相談しながら奮闘。環境に優しい栽培に向けて化学肥料や農薬は使わず、お米の籾殻や牛糞を集めて試してみたり、ミネラルを豊富に含む炭を撒いてみたりと試験を繰り返し、今年から本格的に栽培がスタートしました。
現在は高品質な天然藍のペーストを製造することを目的に、畑に併設した新たな工房を建設中。ゆくゆくは、そこに藍染めの研究・展示センターとしての機能も加え、旅行者が訪れたいと思うようなノンブアランプー県の観光スポットにしたいと、村の発展に繋がる観光資源としての将来も描いています。
工房から広がるグッヘー村の未来
「地球にも人にも優しい藍染めを追求したい」
野口さんが手掛ける藍染めの製法は、日本の伝統製法をベースにタイ式を組み合わせ、独学で見出したもの。もともとは日本の製法をそのまま踏襲しようと思っていたところ、タイの藍との相性なのか、気候の問題なのか、藍を染める前の発酵段階で不具合が生じるなど悪戦苦闘。そこでタマリンドを使用するといったタイの手法を取り入れながら試行錯誤を繰り返し、日本とタイの技術を融合した今のスタイルを導き出したのだそう。
藍に込めたメッセージは「伝統を日常に」
そんな野口さんが「SILK&HOPE」のプロダクトに込めているのは、「伝統を日常に」というメッセージ。「伝統」がゆえに少々格式高さを感じたり、現代のスタイルとはかけ離れてしまい、使用場面がなかったりというギャップが生じることは日本でも少なくありません。タイの藍染めに同様の現象を感じた野口さんは、日常的に藍染めを楽しめるような製品づくりを心がけていると言います。
着心地にもこだわり、生地にはある企業で独自開発されたコラーゲンファイバー(魚の鱗から抽出した特殊な繊維)を使用。袖を通すと、柔らかくサラッとした肌触りと通気性の良さを感じることができます。
「素材によって、色の出方が違うのも藍染めの魅力です。ぜひハンドメイドならではの味わい、その時々の色合いをお楽しみください。最近はジーンズやTシャツの他、アロハシャツや古着を藍で染め直したリメイク再生にも取り組んでいます」。
認知度が少しずつ拡大
村の人にも変化が
工房を開設して約1年が経ち、最近ではタイ文科省や市長が視察に訪れるなど「SILK&HOPE」の名前と製品に対する認知度は少しずつ拡大。また、タイ王国・内閣科学技術省監督下の独立行政法人NIA(National Innobation Agency)による地域活性化プロジェクトの対象団体に選ばれ、資金を含めたサポートを受けるなど今後の活動に期待が寄せられています。
こうした変化に伴い、「SILK&HOPE」を見る村の人たちの目も変わってきたとスィリポーンさんは言います。
「ここには、いわゆる昔の村社会のような閉鎖的な見方が残っており、私たちが工房を開設した当初は『外から来た人が何をやっているんだ』『どうせ失敗する』といった目で見られていましたね。新しいものに対して、どうしても否定から入ってしまう。母親も村の一人として、はっきりと口には出してはいなかったものの最初は反対していたと思います。けれど時間が経つにつれ、私たちがやっていることを理解してくれたのか、今では工房を手伝ってくれるサポーターの一人。応援してもらえるようになれたのは嬉しいですね」と笑顔を見せます。
「私たちの活動を通して村の選択肢を増やしたい」
スィリポーンさんが故郷に戻ってきた目的の一つが、前項で野口さんが言及していた村の支援と発展。古くからの風習を守る意識が強い村の体質を知るからこそ、自らの日本留学の経験を踏まえ「自分の手で世界を広げることができる」「選択肢は自分で増やすことができる」ことを子どもたちを中心に伝えていきたいと言います。同時に、働き口がないために20~30代の若者のほとんどが外へ出てしまうという現状も変えていきたいのだと。
「村自体の活気も薄れていると感じますし、村の人たち自身が『ここには何もない』と思ってしまっているのが現状です。みんなが戻ってきたいと思える、みんなが誇りを持てるような場所をつくることが私の夢です。工房が大きくなれば雇用にも繋がります。少しずつ変えていければ」。
スィリポーンさんが学生時代の頃から口にしていた想いは野口さんへと派生し、「SILK&HOPE」の歩みは村の未来へと繋がっていきます。
SILK & HOPE
住所:3/1 moo2 Khudhea Naklang Nongbualamphu 39170
電話:082-290-9083
E-mail:yumenomorith@gmail.com
【商品の購入・お問い合わせは下記まで】
WEB:https://silk-hope.bentoweb.com/jp
Facebook:DYE-KRAM-工房-by-SILK-HOPE
MAP